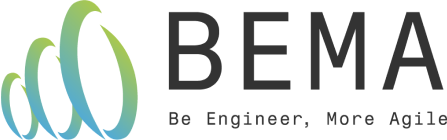BEMA賞 受賞者に聞く、“楽しく”続けてチャンスを掴むアウトプット術
こんにちは、BEMA Lab編集部の濱松です!
BEMA賞※ を受賞された田原葉さん、兼子大地
さん、山岸 玄斉
さんの3名にインタビューを行いました。
※BEMA賞とは、特定の期間に本メディアでアウトプットしてくださった社内メンバーを対象に成果だけでなく、その人の行動や姿勢、そこに込められた価値にも目を向けて表彰する企画です。
業務で多忙な中でも、前期だけで4記事以上のアウトプットを継続したお三方。
「なぜそんなに書けるの?」
「ネタ切れしないの?」
その“ヒケツ”を探ってみると、そこには義務感ではなく、「心理的なハードルを下げる工夫」と「未来の自分を助けるマインド」がありました。
今回は、そんなお三方の素顔や、アウトプットを“楽しく”続けるための考え方に迫ります。
① 生成AIが「書く勇気」をくれる!心理的ハードルの下げ方
兼子さん流
「自分が書いた」と思わなくていい
今回、インタビュー開始早々、私がいちばん衝撃を受けたのが兼子さんのこの発想です。
兼子さんは、自分で書いた文章を生成AIに直してもらい、綺麗に整えてもらうプロセスを必ず挟むそうですが、 面白いのはその解釈。
「AIに直してもらうことで、『これは最終的に生成AIが作ったものだ』と思えるようになるんです」
「自分が書いた」と思うと、「間違っていたらどうしよう」「恥ずかしい」というプレッシャーがかかりますが、「AIが作った」と思えばその心理的ハードルが劇的に下がる。このマインドセットのおかげで、多くのアウトプットを出せるようになったそうです。
【編集部ボイス(濱松)】
「完璧に書かなきゃ」という気持ちが、アウトプットの最大の敵だと改めて感じました。
AIを“自分の代わり”ではなく、“心理的なクッション”として使う発想は、特に最初の一歩に悩む方ほど、救われる考え方だと思います。
田原さん流
構想段階での「壁打ち」が鍵
田原さんも同様にAIを活用していますが、使い所は「書き出しの前」。 構想段階でAIと「壁打ち」をして記事構成を磨くことで、早い段階で「これなら書ける」という納得感を得てから執筆に入ります。 「何を書こうか」と悩む時間を減らし、構成を固めてから書き出すスピード感が、年明け(2026年)から4件提出という驚異的なペースを支えていました。
② アウトプットは未来の自分に伏線を貼る!
山岸さん流
SOSにもチャンスにもなる
山岸さんにとってアウトプットとは、周囲に自分の存在や考えを知らせる「シグナル」を送ること。
発信し続けることで、「ここに詳しい人がいる」「この人は今こんなことで悩んでいる」と伝わり、苦しい時に手を差し伸べてもらえたり、新しい仕事のチャンスが巡ってきたりするそうです。
【編集部ボイス(濱松)】
アウトプットは「評価されるためのもの」だと思いがちですが、本質的には「自分は今ここにいる」というサインなのかもしれません。
インタビューをしていて、山岸さんの言う“シグナル”という言葉がとても腑に落ちました。
私もこの言葉、ひっそり使わせてもらおうと思います!
「伝わる」ようになるには時間がかかる
一方で、最初から完璧に発信できたわけではありません。山岸さんは「アウトプットの価値を理解し、しやすくなるには年月が必要であり、経験を積むことで自分の考えをうまく発信できるようになった」と語ります。
実は山岸さん、以前は「ITに詳しくないお客様に対して技術を伝える」という業務経験を積まれていました。相手にどう言えば伝わるか?と試行錯誤したその泥臭い経験こそが、今の「伝わるアウトプット」の土台になっているのです。
「葛藤」こそが共感を呼ぶ
そんな経験があったからこそ、若手向けの記事依頼を受けた際、あえて「中堅・ベテランとしての葛藤」を正直にさらけ出すことができました。 綺麗な成功談だけでなく、悩みや乗り越え方を共有することが、結果として多くの共感を呼んだのです。
田原さん流
会社の看板を背負うプロ意識
一方、田原さんのモチベーションの源泉は、徹底した「プロ意識」と「学習戦略」にありました。
田原さんが実践しているのは、学んでから書くのではなく、「書くために学ぶ」というサイクル。 例えば、Flutterの技術記事を書いた際は、「BEMAの記事にする」というゴールを先に設定し、そこに向けて学習を進めたそうです。
また、「自分の名前だけでなく、会社の看板を背負って発信している」という強い責任感も特徴的です。 一見プレッシャーに聞こえますが、田原さんはこれをポジティブに利用しています。看板があるからこそ、生半可なことは書けない。だからこそ必死に調べ、検証し、技術を深掘りする。 このプロセス自体が「アウトプット駆動学習」となり、記事の信憑性を高めると同時に、自身のエンジニアとしての技術力を飛躍的に進化させています。
③ アウトプットが生まれるのは、「安心できる場所」があるから
兼子さんが行ったのは、優秀なメンバーに「BEMAという場所があるよ」と伝え、レビューや共同執筆で心理的ハードルを取り除くことでした。
実際に、元々はアウトプットしないタイプだったという山岸さんも、兼子さんからの「ここなら書けるよ」という声かけとテーマ提案があったからこそ、書く量が増えたと語っています。
ゆるやかなレビュー文化
こうした声かけを支えているのが、ガチガチに固めすぎない「ゆるやかな協力体制」です。
兼子さん(デブオプスリードカンパニー):Notionに記事を書いて共有し、自発的にメンバーがコメントする相互レビュー形式
田原さん(クロスアプリケーションカンパニー):稼働状況を見ながら「お願いします」と声をかける柔軟なスタイル
田原さんのカンパニーでは、まだ体系的なレビュー体制はないものの、メンバーの状況を思いやりながら協力を仰ぐ姿勢が、チームのアウトプットを支えています。
【編集部ボイス(濱松)】
「書きなさい」と管理するのではなく、「一緒に書こう」「ここなら安心だよ」と声をかけられる場所をつくること。
エンジニアが蜂の蜜を運ぶように自然と集まる、そんな環境こそが、執筆の輪を広げるチームづくりの第一歩なのだと感じました。
編集部まとめ:AIとチームの環境を味方に、まずは「書いてみる」ことから
最後に、皆さんの今年の意気込みを伺いました:
田原さんはOSS(Open Source Software)開発への挑戦
山岸さんは音声AIや簿記の学習記録
兼子さんはラボ活動での知見共有
と、お三方の挑戦は、これからも続いていきます。
今回のインタビューを通して感じたのは、アウトプットは才能やスキルのある人だけがするものではなく、「続けられる環境」を選び、未完成な自分を受け入れることから始まるということでした。
私自身も、以前はアウトプットの価値をはっきりと言語化できていませんでした。それでも、外部イベントへの参加や個人ブログでの発信を重ねる中で、少しずつ「言葉にすること」が自分や周囲に与える影響を実感するようになりました。
「書いてみたいけど、自信がない」
「何を書けばいいかわからない」
「でも、あの人の記事、なんかいいな…と心惹かれる」
そんな気持ちが少しでもあるなら、それはもう十分なスタート地点です。
まずは、今感じていることを、ほんの少しだけ言葉にしてみませんか?
この記事を書いた人

What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile